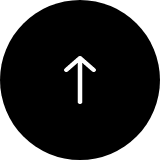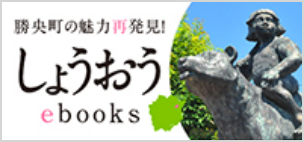ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
教育計画
令和7年度 勝央町立勝央北小学校 学校経営計画
◆学校教育目標 「自ら学び 心豊かで たくましく生きる児童の育成」
◆めざす学校像(一人一人の子ども・教職員により)
- 笑顔がたくさんある学校(協働的に生き生きと活動)
- チャレンジする学校(夢や希望に向かって、主体的に、粘り強く、互いに高め学び合う)
- 期待され、信頼される学校(地域や社会との連携、協力)
◆めざす子ども像
- やさしく
- 相手の気持ちを考える温かい心情、判断力のある子ども
- 自分の良さを知り、励まし合い、高め合う子ども
- 相手を意識して、あいさつができる子ども
- かしこく
- 夢や希望に向かって、実感の伴った基礎的な知識及び技能を伸ばし生かそうとする子ども
- 行動や感情をコントロールして、自分自身の現状に照らし合わせ、力を発揮する子ども
- 学び方を学び、課題発見、解決に必要な思考力、判断力、表現力を高めようとする子ども
- たくましく
- 健康で、調和のとれた運動能力とそれらを支える体力を高めようとする子ども
- 夢や希望に向かって、チャレンジし、ねばり強くがんばり、やり抜こうとする子ども
- より良い地域や社会の実現をめざし、積極的に関わろうとする子ども
◆めざす教職員像
- 児童への愛情<児童理解・人権教育の推進>
- 目の前の子どもへ愛情をもち、一人一人の良さや可能性引き出す教職員
- 特別支援教育を基盤にして児童理解を深め、人権教育を推進する教職員
- 教育への情熱<校内研修の充実・授業改善の推進>
- 個々の児童の実感を伴った理解を目指し、ICTを効果的に活用し、個別最適な授業作り を自ら求める教職員
- 教材研究を深め、児童と一緒に成長を喜ぶ、学びを止めない教職員
- チーム力<連携の強化>
- 地域や家庭と連携し、チームを意識して学び高め合う教職員
- 子供や家庭とのつながりを大切にし、どの子も伸びる学校改善を推進する教職員
◆指導の重点
- 自己選択や意思決定と、振り返りによる主体的な学び手の育成
- 「聴くときは、賢くなるとき」を合い言葉に「受容」と「共感」を大切にした学級づくり
- 児童につけさせたい力、学習過程やゴールイメージを児童と共有し、スモールステップに より達成感をもたせ、過ちから学び、粘り強く挑戦し続けようとする意識を醸成 ・学習内容を生活に結びつけ、「自分の考えを持ち、友だちと伝え合い学び合い、そのよさ を振り返る」、主体的な学び手を育成する授業作り
- 児童の自己調整学習による個別最適な学びの実現
- チャイムスタート等の学習規律が必要な理由を考えさせる
- 学校、家庭の学習で効果的なICT活用と、情報モラルや情報安全教育の推進
- 人権意識の向上、体験的な学びの充実、協働的で創造的な学び手の育成
- 教職員自身も人権意識を高め、いじめ、障害者理解等、人権教育を着実に実施
- 豊かな体験的学びのある授業作りと自分事として考え内容項目に迫る道徳の授業作り
- 体力と自己肯定感・自己有用感の向上
- 体力アップタイムを設けた授業作り
- 視野を広げ、なりたい自分の意識化に資する機会(各地、各年代、様々な人との交流)の 充実
- 授業や行事で児童が活躍できる場、挑戦する場の設定
- 協働的指導(正副担任制)体制の確立、教科担任制の研究推進
- 正副担任制による支援体制の充実と発達段階を考慮した専科やTtの配置
- ICT活用を探究し、Ud等の特別支援教育の視点を生かした指導や支援の工夫
- 整理、整頓や時宜にあった掲示、学習成果の掲示など、落ち着いた学習環境づくり
◆指導に関わる留意事項
- 一人一人が力を伸ばす主体的な学びと振り返り
- 意識を高くして、主体的に学ぶ授業作り
- ユニバーサルデザイン教育、特別支援教育の視点(焦点化・視覚化・共有化)を生かし、 スモールステップによる評価と振り返りで、見通しが持てる、わかった、できたの授業
- しっかり事象を捉え、理解して判断できる確かな読解力を育てる授業
- ふんだんにICTを活用する授業
- 探求的な学習を取り入れ、自分の考えを持ち、友だちと伝え合い学び合うよさを、振り 返りにより感じられる授業
- Ojtを生かした協働的な教材研究の充実
- 児童と教師の協働による落ち着いた学習環境
- 児童の自己有用感、効力感をベースとした、学習規律の定着(チャイムスタート、聞き 方・話し方、学習用具)による落ち着いて学べる雰囲気作り
- コミュニケーションスキルの指導、自治的活動の充実による安心して学べる集団づくり
- 協働指導体制、教科担任体制による学習環境を研究/3基礎基本の定着
- ICTの活用を含めた朝学習、家庭学習の充実(反転学習の推進)や学習内容の定着 (きんとくんノート&きんとくんプリントの積極的な活用)
- 学習した事をアウトプットする、学びを生かす場面を積極的に設定
- 学力調査等の結果分析とつまずきの早期発見、適切な指導、支援と補充時間の確保/既習事項の反復練習、既習事項を活用した課題解決による基礎基本の定着(システム 化)
- 特別支援教育の充実
- 個に応じた指導及び支援、学びに向かう環境整備の工夫
- 「見通し」「達成感」がもてる学習活動の工夫
- 定期的な情報交換、ケース会による情報共有と指導の一貫性の確立
- 読書の習慣化
- 読書する場の設定(朝読書、読み聞かせ、家読の取組等)
- おすすめの本、学級文庫 ・委員会活動による読書推進
- 意識を高くして、主体的に学ぶ授業作り
- 人権を意識し助け合い、認め合い、高め合う集団づくり
- 積極的な生徒指導の推進~生徒指導の四機能を生かして~
- 「自己存在感の感受」「共感的な人間関係の育成」「自己決定の場の提供」「安全・安 心な風土の醸成」を意識した学習活動、探究的な学習の推進
- 縦割り班活動や異学年交流の工夫
- 一人一人が大切にされ、自分の思いを出せる居心地の良い学級づくり(Qu調査の活用)
- Kintoくんミニアンケート、教育相談タイムをはじめ、児童の気持ちを聞く機会の 確保
- コミュニケーションスキルの一つとして、正しい言葉遣いやあいさつの意識づけ
- 人権教育の推進
- 人権感覚の醸成(人権教育を着実に実施。言葉遣い等、日常に生かす人権感覚)
- 人権課題への取組(いじめ、福祉等、教科等の学習の中でも、人権課題を焦点化)
- 手元に広がる豊かな体験的学びや学校内外で地域や人との交流から学ぶ授業作り
- 児童の道徳的心情を湧き上がらせる主体的・対話的な道徳の授業作り
- 積極的な生徒指導の推進~生徒指導の四機能を生かして~
- 体力、自己肯定感・自己有用感の向上
- 保健体育学習の充実 ・角力、サーキット、チャレンジランキングの取組
- 「体力アップ・マイベストチャレンジシート」の活用
- 委員会活動による体育集会、保健集会等
- 基本的な生活習慣の定着支援、メディアコントロールの推進
- 外遊びの活性化 ・外遊びの推奨、外遊びがしたくなる環境づくり(北小ギネス、一輪車など)
- 児童が活躍できる場、挑戦する場の設定
- 自分から関係する他者へ働きかける場の設定
- 学級活動、縦割り班・委員会活動など、子どもが考え、計画する活動の充実
- 行事、探究的で体験を伴う学習の充実(スポフェス、米作り・黒豆作り、福祉体験等)
- 一人一人が認められる機会の充実(記録証や賞状等を出せる機会の設定)
- めあてに向けて頑張ったことを実感できる、めあてや振り返りの工夫
- 縦割り班活動や異学年交流を、なりたい自分へ意識を高める工夫
- 保健体育学習の充実 ・角力、サーキット、チャレンジランキングの取組
- 地域・家庭と共にある開かれた学校づくり
- 地域の方々との交流
- 学校運営協議会と学校支援協働本部を両輪としての推進
- 北小まつり(11月29日)、クラブ活動、地域ボランティア、外部講師
- 積極的な情報発信と公開
- 業務を見直し、児童を伸ばす学校改善の推進に向けた連携
- 地域に学び、地域と関わり、地域へ働きかける、地域への愛着を持つ体験的な地域学習
- 生活科や総合的な学習の時間を中心に探究的、体験的な学び
- 地域を支えている方々から学び、学んだ事を生かした地域への働きかけ
- 自立に向けた家庭との連携
- 望ましい生活習慣の定着(「ぱっちりモグモグ」、PTAを中心とした家庭読書、お手 伝い)
- “お”弁当の日などによる、親子のふれ合いの推進
- 親プロの推奨
- 情報モラル、情報安全教育の推進と家庭学習時間の確保
- 地域の方々との交流