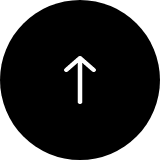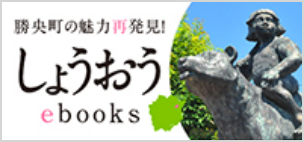本文
国民年金加入者・受給者が亡くなったとき
身近な人が亡くなった場合、ご遺族様が手続きをすることで、以下の年金を受け取ることができる場合があります。
未支給年金の請求
未支給年金とは?
年金は、受給者が亡くなった月の分まで支払われますが、受給者が亡くなったことにより、支給されずに残っている年金(以下「未支給年金」といいます。)がある場合、受給者と生前に生計を同じくしていた遺族が請求をすることで、未支給年金が遺族に支給されます。
未支給年金を受けることができる人及び順位
亡くなった人と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
※3親等内の親族については、こちら(クリックするとリンクページに移動します) <外部リンク>をご確認ください。
<外部リンク>をご確認ください。
生計を同じくしていた遺族とは?
死亡日において、以下のいずれかに該当する遺族のことをいいます。
- 亡くなった人と住民票上同一世帯に属していたとき
- 亡くなった人と住民票上別世帯ではあったが、住民票上の住所が同一であったとき
- 亡くなった人と住所が住民票上異なっていたが、次のいずれかに該当していたとき
- 起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていたと認められるとき
- 亡くなった人に対して生活費、療養費等の経済的な援助が行われていたこと、又は亡くなった人から生活費、療養費等の経済的な援助が行われていたこと 等
請求に必要なもの
- 亡くなった人の年金証書
- 亡くなった人と請求する人の続柄が確認できる書類(戸籍謄本(親子の場合、請求者の戸籍抄本でも可)又は法定相続情報一覧図の写し等)
- 請求する人の住民票(世帯全員で、世帯主及び続柄が記載されたもの)
- 請求する人の受取金融機関がわかる書類の写し
- 生計同一関係に関する申立書(亡くなった人と請求する人が別世帯の場合のみ。対象者には、別途窓口でお渡しします。)
- 請求する人の個人番号がわかる書類(未支給年金請求書に請求者のマイナンバーを記載することで3.の書類を省略できます。また請求者が配偶者である場合は、マイナンバーの記載により、2.の書類も省略できます。)
請求上の注意
- 戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。
- 年金請求のためにご用意いただいた戸籍謄本等を年金請求以外で利用される場合は、戸籍謄本等の原本をお返しします。原本返却が必要な時は、お申し付けください。
- 未支給年金請求書に金融機関の証明を受けた場合、4.の書類は添付不要です。
- マイナンバーカードに登録した公金受取口座を利用する人は、金融機関の証明及び4.の書類は添付不要です。
- インターネット専業銀行での年金の受け取りについては、年金Q&A「インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。」(クリックするとリンクページに移動します)
 <外部リンク>を参照してください。
<外部リンク>を参照してください。 - 共済年金を受給していた人が亡くなった場合、加入していた共済組合又は日本年金機構のどの窓口でも未支給年金の請求を受付(ワンストップサービス)できる場合があります。ただし、地方公務員共済組合員期間のみ(単一共済者)で、かつ以下の条件に該当する人は、加入していた地方公務員共済組合に請求してください。
- 被保険者期間が地方公務員共済組合員期間のみの老齢基礎年金を受けている人
- 被保険者期間が地方公務員共済組合員期間のみの人が亡くなったことによる遺族基礎年金を受けている人
- 初診日が地方公務員共済組合員期間中にある障害基礎年金を受けている人
遺族年金の請求
遺族年金は、国民年金又は厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった人の年金の加入状況などによって、いずれか又は両方の年金が支給されます。
- 詳しいことは、「遺族年金」(クリックするとリンクページに移動します)
 <外部リンク>をご参照ください。
<外部リンク>をご参照ください。
死亡一時金の請求
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その人によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
- 詳しいことは、「死亡一時金」(クリックするとリンクページに移動します)
 <外部リンク>をご参照ください。
<外部リンク>をご参照ください。
寡婦年金の請求
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 詳しいことは、「寡婦年金」(クリックするとリンクページに移動します)
 <外部リンク>をご参照ください。
<外部リンク>をご参照ください。
各種年金の申請について
本町では、税務住民部窓口において、亡くなった人のご遺族様に対し、死亡後に必要な各種手続きをご案内しております。年金に係る死亡後の手続きは、亡くなった人が加入していた年金制度や生計を同じくしていた人の状況等により異なりますので、ご遺族様が来庁された際、個別に申請先や申請書の記入方法、ご提出いただく書類等についてご説明させていただきます。
また上記年金の請求手続きについては、お近くの年金事務所の窓口で行うこともできます。
お問い合わせ先
- ご遺族様への亡くなった人に係る死亡後の手続き案内について
【勝央町役場 税務住民部】
〒709-4316
住所:岡山県勝田郡勝央町勝間田201
電話:0868-38-3116
- 年金事務所の窓口で年金請求手続きや年金相談をご希望の場合
【日本年金機構 予約受付専用電話】
電話:0570-05-4890
(050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6631-7521へご連絡ください)
※日本年金機構では、全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。津山年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する人は、予約相談をご利用ください。詳しくは、「年金相談についてのご案内」(クリックするとリンクページに移動します) <外部リンク>をご参照ください。
<外部リンク>をご参照ください。
関連リンク
- 日本年金機構HP「身近な方が亡くなったとき」(クリックするとリンクページに移動します)
 <外部リンク>
<外部リンク>