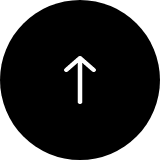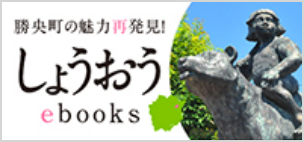本文
福祉医療費助成制度の所得区分・自己負担限度額・償還給付について
医療機関・薬局等(以下、医療機関等という)の窓口に、「マイナ保険証・資格確認書等(いずれか1点)」と「受給資格証」を提示することで、保険診療にかかる自己負担額から一部負担金を引いた額を公費で負担します。医療機関等で支払う一部負担金は、受給資格証を提示することで1割負担(※)となります。


なお、受給資格者や受給資格者と生計を一にする方の所得によって、所得区分と負担上限月額が設けられています。
※乳幼児および児童生徒等医療費受給資格証については、無料で診療等を受けられます。県外等の保険診療で患者負担分が発生した場合は、当ページ下の「窓口の償還給付」を参照してください。
※障害者医療費受給資格証のうち、精神障害による認定を受けている方は、助成内容に一部制限があります。
以下の内容は、主に障害者医療費受給資格証、ひとり親家庭等医療費受給資格証になります。
所得区分
福祉医療費助成制度では、所得に応じて下記の4区分あります。
| 一定以上 | 町民税課税所得が145万円以上の方と同じ世帯にいる方 |
|---|---|
| 一般 | 世帯全員が町民税課税所得145万円未満 |
| 低所得II | 世帯全員が町民税所得割非課税 |
| 低所得I | 世帯全員が町民税所得割非課税かつ世帯全員の合計所得金額なし |
※所得区分は、毎年7月から前年(1月~6月は前々年)の所得に応じて判定します。
※所得区分は年度途中でも変わる場合があります。
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来のみ | 外来+入院 |
|---|---|---|
| 一定以上 | 44,400円 | 80,100円+1%(注) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得II | 2,000円 | 12,000円 |
| 低所得I | 1,000円 | 6,000円 |
(注)自己負担額80,100円を超えたときは、80,100円+(医療費総額-801,000円)×1%
※上記金額表は制度改正によって変わることがあります。
医療費の給付について
受給資格者は、資格証を利用すると1割負担で医療機関等を受診することができますが、例えば県外の医療機関等を受診したときは、受給資格証が利用できませんので、健康保険の負担割合(例:3割負担)で受診することになります。
例
- 県外の医療機関等で受診したとき
- 保険適用の診療等であったが、10割負担したとき(補装具利用の治療、整体の治療など)
- 複数の医療機関等を利用し自己負担限度額(月額)を超えているとき
そこで、本来の福祉医療助成制度を利用していただくため、差分を償還する方法があります。
差額の償還給付
該当助成制度:障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度
1ヶ月間で、医療機関等の窓口に支払った一部負担金の合計が上表の自己負担限度額を超えている場合は、その差額を償還給付として支給します。ただし、初回の支給は申請が必要です(2回目以降は自動支給)。
なお、償還給付の支給は、対象診療月から3~4ヶ月後の振込になります。
窓口の償還給付
該当助成制度:障害者医療費助成制度、乳幼児及び児童生徒等医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度
下記の2点など、保険適用でも資格証利用できなかった場合、償還給付を受けるには申請する必要があります。
なお、償還給付の支給は、申請月から1~2ヶ月後の振込になります。
- 県外の医療機関で資格証が使えず、療養を受けた場合
- 補装具の装着等で資格証が使えず、療養を受けた場合
★次の1~5を準備して役場へ給付申請してください。
- 下記給付申請書のどちらか
「給付申請書(領収書方式)」 [PDFファイル/299KB]
「給付申請書(医療機関証明方式)」 [PDFファイル/146KB](注) - 医療機関等の領収書(医療機関が直接証明する申請書(ピンク色)の場合は不要)
- 資格情報のお知らせ/資格確認書/マイナ保険証等(いずれか1点)
- 受給資格証
- 申請者の振込口座がわかるもの
注:色が付いた申請書です。カラー印刷またはピンク色用紙で印刷してください。
※ マイナ保険証で健康保険情報を確認する場合、マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号をご用意ください。
※ 健康保険各法の療養費に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ療養費の請求する必要があります。
※ 健康保険の保険者(主に社会保険)に療養費の請求する場合は、医師の証明書(原本)や領収書(原本)を要求されますので、あらかじめコピーし保管してください。健康保険が償還決定をした際には支給決定通知書が郵送されます。
その後、福祉医療(勝央町)に償還給付を請求するときに、医師の証明書(コピー分)、領収書(コピー分)、支給決定通知書(原本)を提出してください。
受付窓口
原則、ご本人または世帯主や保護者が手続きしてください。
受付・お問い合わせ窓口
勝央町役場 税務住民部 医療班
勝央町勝間田201番地 Tel:(0868)38-3115
受付時間
開庁日 8時30分~17時15分(平日のみ・日曜窓口は利用不可)
※ページ下部の業務時間を参照
手数料
不要